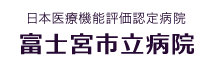病院案内
院内感染対策指針
Ⅰ.目的
この指針は、院内感染の防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、富士宮市立病院における院内感染対策体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
Ⅱ.院内感染対策に関する基本的考え方
医療機関においては感染症の患者と感染症に罹患しやすい患者とが同時に存在していることを前提に、医療行為を行う際に必然的に起こりうる患者・職員への感染症の伝播リスクを最小化するとの視点に立ち、全ての患者が感染症を保持し、かつ罹患する危険性を併せ持つと考えて対処する「スタンダードプリコーション」の観点に基づいた医療行為を実践する。あわせて感染経路別予防策を実施する。
1.病院内外の感染症情報を広く共有して院内感染の危険および発生に迅速に対応する。
2.院内感染が発生した事例については、速やかに評価して、事例を発生させた感染対策上の不十分な点や、その根本的原因を調査し改善する。
3.院内感染対策活動の必要性、重要性を全部署及び全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行い、患者に信頼される医療サービスを提供して、医療の質の向上に寄与することを基本姿勢とする。
Ⅲ.院内感染対策のための委員会(院内感染対策(管理)体系図 参照)
1.院内感染対策委員会
院内感染対策に関する問題点を把握し改善策を講じるなど、院内感染対策活動の中枢的な役割を担うために、院内感染対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。
1)「業 務」
① 院内感染対策の検討・推進
② 院内感染防止の対応及び原因究明
③ 院内感染発生状況に関すること
④ 感染予防の教育・啓発に関すること
⑤ その他院内感染予防のための対策に必要と思われる事項に関すること
2)「構 成 員」
委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
① 委員長は、病院長とする。
② 委員は、次の者をもって充てる。
副院長、診療部長、診療技術部長、薬剤部長、看護部長
副看護部長、事務部長、病院管理課長、医事課長、
臨床検査科長、栄養科科長、手術室師長、感染管理認定看護師
2.ICT(感染制御チーム)
院内感染対策として職員の健康管理・教育・感染対策相談(コンサルテーション)・発生動向監視(サーベイランス)・対策の適正化・および介入を行う。
院内感染対策委員会の下部組織として、感染対策に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど、院内感染対策活動の実践チームとしての中心的な役割を担う。
1)「業 務」
① 院内感染対策に関する教育・研修の企画および運営、ICT通信の発行
② 感染対策相談・院内感染対策に関する疑問の解決
③ 院内感染症発生状況の把握と感染症情報の共有
JANISサーベイランスへの参加
J-SIPHEサーベイランスへの参加
④ 院内感染防止マニュアルの作成と定期的な見直し
⑤ 抗菌薬の適正使用
⑥ アウトブレイクが疑われた場合の対処
⑦ 職員の院内感染症予防
⑧ 院内ラウンド
1週間に1回程度、年間計画で定められた部署のラウンドを行う。ラウンドは可能なかぎり医師・看護師・薬剤師・検査技師と関係部署の担当者が参加する。
⑨ 地域の感染対策ネットワークの推進
2)「構 成 員」
① 委員会は、委員長・副委員長各1人及び委員若干名をもって組織する。
② 委員は、診療部・診療技術部・薬剤部・看護部・事務部の各部長が推薦し、院長
が指名した委員をもって組織する。
③ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
a.医師の役割
ア.ICTメンバーに業務担当を指名する。
イ.医療関連感染に関する医療の質の管理を行う。
ウ.ICTの活動方針について説明し、各診療科の価値の理解に努める。
エ.個々の患者の感染症についてコンサルテーションを行う。
b.看護師の役割
ア.医療関連サーベイランスを活用する。
イ.感染症発生時に感染対策の実施状況を把握する。
ウ.委員会のファシリテーターを担い、看護部感染対策委員会と連携する。
c.臨床検査技師の役割
ア.感染症発生状況を速やかに関係各署へ報告する。
イ.感染情報レポートを作成する。
ウ.耐性菌サーベイランスの評価をする。
エ.アンチバイオグラムを作成し周知する。
オ.適切な材料採取に対する指導及び説明をする。
カ.必要時、環境検査を実施する。
d.薬剤師の役割
ア.自施設の抗菌薬使用状況を分析する。
イ.抗菌薬届出制の運用状況を把握する。
ウ.抗菌薬使用コンサルテーションを行う。
エ.抗菌薬使用に関するマニュアルの作成・改訂
オ.抗菌薬の治療薬物モニタリング(TDM)
カ.ワクチン関連の法規やガイドラインなどの最新情報を確認する。
3)「報告・答申・議事決定事項」
① 委員会は、委員会が調査研究した事項について報告書を作成し、院長に報告しなければならない。
② 委員会は、委員会の議事について議事録を取りまとめ、院長に報告しなければならない。
③ 委員会は、院長から諮問を受けた場合には、諮問事項に関する審議を実施し、答申書を取りまとめ、院長に答申しなければならない。
④ 委員会の議事決定事項は、院長の承認(決裁)後、効力を発する。なお、予算執行を伴う等重要事項については、病院運営委員会に審議を付託する。
⑤ 委員会の議事決定事項は、代表者会議において発表・連絡し、院内における周知・徹底を図る。
3.看護部感染対策委員会
ICTと協働して富士宮市立病院看護部における感染防止を図り、看護の質の保証を目的とし、毎月1回定期的に定例会を持つ。
1)「業 務」
① ICTと連携をとる
② 感染防止に対する啓発活動をする
③ 感染防止の実践行動のリーダーシップを担う
④ 針刺し事故の原因分析並びに再発防止策の検討および提言
⑤ 院内関係部署との連携を図る
⑥ その他感染防止に関すること
2)「構 成 員」
① 各看護単位代表者。
② 委員長は看護部長が指名したものとする。
副委員長1名、事務局1名は委員の互選で決める。
4.AST(抗菌薬適正使用支援チーム)
ICTの下部組織として、ARM対策に取り組み、抗菌薬の適正使用を推進する。
1)「業 務」(抗菌薬適正使用指針参照)
① ICTと連携をとる
② 抗菌薬適正使用に関する研修の企画
③ 抗菌薬適正使用のためのマニュアル作成と見直し
④ モニタリング患者のカンファレンス
対象患者に対して、適切な微生物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、抗菌薬の選択・用法・用量の適性性、有害事象の有無、TDMの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行なう。
⑤ その他抗菌薬適正使用推進に関すること
2)「構 成 員」
① 抗菌薬に専門的知識を持った医師・薬剤師・臨床検査技師・看護師
② 部会長は院長指名、部員は各部門の推薦に基づき病院長が指名する。
4.感染対策室
当院における医療関連感染を防止し、ICTと協働して組織横断的に感染管理活動を行う部門をいう。感染対策室には、感染管理認定看護師が専従配置され、院内の感染症情報の収集・分析、アウトブレイクの原因と防止策の検討提言、感染対策に関する相談を行う。
1)「業 務」
① 医療関連感染防止に必要な感染対策に関すること
② 医療関連感染防止対策の啓発・教育に関すること
③ 医療関連感染の発生に関する情報の収集・分析・解析に関すること
④ 医療関連感染に関わるマニュアルに関すること
⑤ 職業感染防止に関すること
⑥ その他感染対策に関すること
2)「構 成 員」
① 室長は病院長とする。
② 室員は感染管理認定看護師と事務員とする。
Ⅳ.院内感染対策に関する職員研修についての基本方針
1.ICTは、全職員対象に講習会を年に2回以上定例開催する。この講習会では院内感染対策に関する教育を行う。
2.ICTは、院外の感染対策を目的とした各種学会・研修会・講習会の開催情報を広く告知し、参加希望者の参加を支援する。
3.看護部感染対策委員会は、リンクナースを教育し、必要に応じて、個別・部署単位・全職員を対象に研修会を開催する。
4.感染対策室は、新規採用職員研修を行い院内感染に関する教育を行う。
Ⅴ.感染症の発生状況の報告に関する基本方針
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるように、各種サーベイランスを実施する。
1.MRSAは、1週間単位で検出患者数・検体数・新規患者数を病棟ごとに集計して院内感染対策委員会に報告する。
2.多剤耐性緑濃菌・ESBLなど注意が必要な細菌は件数を院内感染対策委員会に報告する。
3.カテーテル関連血流感染、人工呼吸器関連肺炎、尿道留置カテーテル関連尿路感染、手術部位感染などのサーベイランスを可能な範囲で実施する。
Ⅵ.院内感染発生時の対応に関する基本方針
1.職員は、院内感染を疑われる事例が発生した場合にはICT委員長に通報する。ICTは詳細の把握に努める。アウトブレイクあるいは異常発生時には、その状況および患者への対応を病院長に報告する。必要な場合にはICT委員の招集を行い、対策に介入する。
2.感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律に規定される診断及び届出の手続きについて担当医師に助言指導する。
3.特定の感染症の院内集団発生を検知した場合は、静岡県・国立感染症研究所などと連携を取って対応する。
Ⅶ.当院の院内感染対策指針の閲覧に関する基本方針
1.本指針は、院内LANを通じて全職員が閲覧できる。また、病院ホームページにおいて一般に公開する。
Ⅷ.院内感染対策推進のために必要なその他の基本方針
1.職員に当院の院内感染対策を周知するため、委員会が別に定めた感染対策マニュアルを各部署に配布し、職員はマニュアルに基づいて感染対策を実施する。
2.ICT職員は、インターネットや報道等で院内感染事例の収集に努め職員の院内感染防止意識の向上を図る。
令和6年5月改定
富士宮市立病院